卒論 Tips10 論理的な展開とは
なぜ、論理的な展開が重要か?
最初に「なぜ論理的な展開が重要か?」について触れておこう。
それは、教授が読むときに重視している割に、学生側の意識が低いからである。
つまり、互いの意識ギャップが一番大きい箇所なのだ。
教授がきみたちの論文を評価する際に、まず何に目を配るか?
というと、それは骨太の構成であり、メッセージである。
ポイントは「何が言いたいのか?」という事と、「それをちゃんと説明/証明できているか?」この2つである。
卒論はいわば、数学の証明問題の様なものなのであり、君らが設定したテーマがきちんと語られているか、証明されているか、にまず目がいくものだ。
この証明過程の流れが論理的か、散文的かを見れば評価の察しはつく。
というのも、複数の学生を対象にしていると、(君らが苦労した割には)、彼らは深くは読めないという事情もあるのかもしれない。
論理的かどうかを簡単に確認してみる
まず最初に、現在、取り組んでいる論文やレポートについて、以下の問いに対する答えを考えてみてもらいたい。
- 結論(論文を通じて言いたい事)は何か?
→環境問題解決には○△が不可欠
→トヨタ経営の秘訣は▲×だった!
→源氏物語の○△の新しい解釈として▲×が可能 - その根拠・理由を明確に示しているか?
→はい/いいえ/ - そのように言える根拠・理由は具体的に何か?
- その根拠・理由は結論を導くのに十分か?
論理的なロジック展開ができているかどうかのチェックポイントはこの4つにつきると言える。
Q1に答える事は単純なようであるが、結論を一言で言いあらわすとなると、戸惑ってしまう方もいるだろう。
考えが広がっている内に、焦点がぼけてはいないだろうか?
“色々調べて、たくさん考えました”ということは伝わってくるが、”要は何が言いたいの?”という論文は少なくはない。
半年~一年の間、同じテーマを考えていると、なかなか客観的に自分の研究内容を捉えて考えることが難しくなりがちだ。
そんな時は、自分が“書く立場”ではなく“読む立場”になって考えてみよう。
Q2の根拠・理由は、散文ではなく、学術的な論文である所以である。
感想文や、私の主観ではなく、根拠・理由に裏付けられた結論を示す必要がある。
試しに、Q3で書いた内容と、Q4で書いた内容を以下のようにつなげてみて、
<Q3の根拠・理由> → ダカラ → <Q1の結論>
と自然とつながるかどうか考えてみよう。
すんなり来るようであれば、最後の問はクリヤである。
Q4はQ3の根拠・理由が質的・量的に十分かどうかというチェックポイントである。
ここで述べた事は抽象的に書いても、“当たり前”すぎると感じ、“自分はできてる”と思いがちである。
是非、“卒論チェック”の論点チェックなどを見てみよう。
それらを参考に、また反面教師としながら、自分の卒論について振り返ってみよう。
次は具体的に納得性を高めるためのテクニックについて紹介したい。
ロジカルシンキングの秘訣
4つの問いの意味、関係はわかったかだろうか?少々抽象的でわかりにくかったかもしれない。
ここでは、おさらいの意味も含め、一味違った角度から、”論理的な展開の納得性を高めるためにどうすればよいか?”その原理原則について少し触れておきたい。
ロジカルシンキング(論理的な考え方)で基本となるのは、下の図にあるようなピラミッド構造で思考を整理することである。
一番上に来るのが、その論文を通して一番言いたい事(=結論)である。
それを導くために、第一章から第三章(通常はもっと多いと思うがここでは三章立てと仮定)が位置づけられており、先ほどの4つのチェックポイントをクリアするかどうかをチェックする。
そして、更に、同じ事が、一段下がった構造においても成り立っているかが重要である。
つまり、第一章で言いたかった事(=結論)は、第一節から第三節の記述から導かれているかどうかである。
このようなピラミッド構造を意識するだけで、論文の構成がイメージしやすくなる。
更に、論理性を高めるには、以下の図で示した、青色の矢印とオレンジ色の矢印の箇所が重要となる。
ここに二つの原則がある。
青色の箇所は「MECE」と呼ばれるもので、オレンジ色の箇所は、「So What / Why so」でつながっているべきものである。
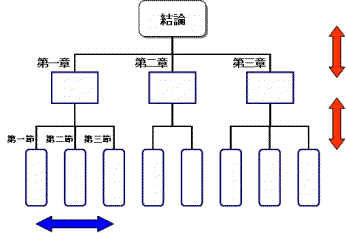
一番目は図でみた時に、第一節から第三節までで示した色々な“情報やデータ”がMECEかどうか?ということである。
このMECEというワードは聞き慣れないものだと思う。
米国発の造語であるが、最近、ビジネススクール等では当たり前のように使われているものである。
Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive の頭文字をとったもので“ミッシー”もしくは“ミーシー”と発音する。
“ある事柄を重なりなく、しかも漏れの無い部分の集合体として捉えること”を意味している。
十分かどうかを判断する時に使える考え方である。
導入部分の“情報・データ”同士が重なりなく、しかも漏れがなく揃っているかどうかをチェックしよう。
二番目は 図でみた時に、第一章から第三章で示した“情報”と、上位に来る“結論”が、
下から見ると、So what(だから何なのか?)に答える内容になっていて、
逆に上から見ると、Why so(本当にそうなのか?)に答える内容になっているかということ。
もう少し噛み砕くと、“第一章から第三章までの情報・データを見て、話を集約すると、結論が自然に出てくる”、と同時に、”結論を具体的に説明すると、その定義が第一章から第三章までの情報・データになっている”という関係になっているということである。
このように上から見ても、下から見ても、両方から見て、話に飛躍が無いかどうかをチェックするということが重要である。
以上の原理原則を意識しておくだけで、少なからず論理的な展開の納得性を高めることができるだろう。
備考
ロジカルシンキングという言葉や概念を見聞きしたり、一度は学んだことのある人は多いと思いますが、実際に使いこなしている人となると、多くはないのが実情です。
ロジカルシンキングは、レポートや論文の構成・流れ・骨組みを設計する上で、非常に役に立つものです。
ですので、一度じっくり勉強してみてください。
紙面の関係上、ここでは上記程度しか説明できませんでしたが、書籍等でマスターすることをお薦めします。
お薦め本はbooks tipsで紹介しています(事例が豊富で実践的な書籍の方がベター)。
また、4年生であれば、「@卒論WEBサポート」でも、卒論に的を絞り無理なく身につけることのできるドリルを用意しています。
